
こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
過去問5年分以上の大学入試の文学史問題を分析した結果から「よく出る問題」だけに絞って出題・解説します。
今回は『土佐日記』を扱います。
そもそも『土佐日記』って何だ?問題解ける気がしないぞ?と思った場合は、基礎知識を整理したページを先に読んでから挑戦してみてください。
では、今回の練習問題に挑戦!
問題
『土佐日記』の作者は誰か。
1.藤原定家
2.紀貫之
3.上田秋成
4.本居宣長
『土佐日記』の成立と同時期に作られた和歌集はどれか。
1.古今集
2.後拾遺集
3.千載集
4.新古今集
↓
↓
↓(答えが出ます)
↓
↓
答え・解説
『土佐日記』の作者は誰か。
1.藤原定家
2.紀貫之
3.上田秋成
4.本居宣長
単純な一問一答問題でした。
『土佐日記』の作者は「紀貫之」です。
『土佐日記』の成立と同時期に作られた和歌集はどれか。
1.古今集
2.後拾遺集
3.千載集
4.新古今集
『古今和歌集』の撰者は、『土佐日記』の作者と同じ紀貫之です。
作者が同じなので、同時代に成立していて当然ですね。
『古今和歌集』の知識も必要な横断問題でしたが、『古今和歌集』と『土佐日記』を関連づける問題は頻出です。
また、『土佐日記』は『源氏物語』以前に成立した作品である、という観点でもよく問題になります。
まとめて覚えてしまいましょう。
※『古今和歌集』について
→【古今和歌集】の特徴まとめ
※『源氏物語』以前に成立した作品について
→【年代攻略】『源氏物語』以前の作品まとめ
・『土佐日記』の作者は紀貫之
・『古今和歌集』は『源氏物語』以前の平安時代に成立
・『古今和歌集』の撰者は紀貫之・凡河内躬恒・紀友則・壬生忠岑
『土佐日記』はココが出る!まとめ
『土佐日記』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『土佐日記』の作者は紀貫之
・『土佐日記』は『源氏物語』以前の平安時代に成立
・『土佐日記』のジャンルは「日記」「紀行」
・『土佐日記』は土佐~京への旅・子を亡くした悲しみを綴る日記
・『土佐日記』の書き出しは「男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり。」

これさえ覚えれば、『土佐日記』関連の大学受験文学史問題の9割は解ける!
今回はここまで。
定着させるために、繰り返し問題を解いてくださいね。
『土佐日記』の基礎知識を確認しておきたい場合はこちらのページを確認してください。

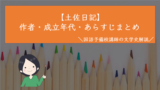


コメント