・【元禄文化期の文学】の基礎知識(作者・成立年代・あらすじ)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは【元禄文化期の文学】の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2019年 学習院大学
・2019年 滋賀県立大学
ほか
【元禄文化期の文学】 基礎知識まとめ
まずは【元禄文化期の文学】の基礎知識を整理します。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 出世景清 | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | ー | ー |
| 曽根崎心中 | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | 実際にあった心中事件を題材とする | ー |
| 冥途の飛脚 | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | ー | ー |
| 国性爺合戦 | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | ー | ー |
| 好色一代男 | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (好色物) | ー | ー |
| 好色五人女 | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (好色物) | ー | ー |
| 日本永代蔵 | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (町人物) | ー | ー |
| 世間胸算用 | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (町人物) | ー | ー |
| 野ざらし紀行 | 松尾芭蕉 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 俳諧 紀行 | ー | ー |
| 笈の小文 | 松尾芭蕉 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 俳諧 紀行 | ー | ー |
| おくのほそ道 | 松尾芭蕉 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 俳諧 紀行 | 北陸・奥州を巡る | ー |
元禄文化は上方の町人文化
元禄文化とは、江戸時代の上方(関西)で発展した町人の文化です。
「元禄」とは江戸時代の元号です(だいたい徳川将軍5代目の綱吉の時代)。
戦いがなくなり、経済が発達して、庶民に余裕が出てきたので文化面がどんどん発展していきます。
肩肘張らずに気楽に楽しめる、娯楽性の高い文学がたくさん出てきて流行します。

庶民による、庶民のための文化!
日本史を勉強している人は、文化・芸術など多岐に渡って覚える事項がありますが、文学史問題では”文学面”に絞って良く出るポイントを押さえましょう。
元禄文化で問題になるのは大きく3ポイント(+1)です。

元禄文化攻略のゴロ合わせは「近い松」!
では「近い松」をカギにしてそれぞれのポイントを見ていきましょう!
【元禄文化の文学作品】よく出るポイント
元禄文化期の文学作品で、よく出るのは「近い松」の3人です。
い:井原西鶴
松:松尾芭蕉
一つずつ確認していきましょう。
近松門左衛門の代表作
近松門左衛門の作品は、以下の4つがよく出題されます。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 出世景清 (しゅっせかげきよ) | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | ー | ー |
| 曽根崎心中 (そねざきしんじゅう) | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | 実際にあった心中事件を題材とする | ー |
| 冥途の飛脚 (めいどのひきゃく) | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | ー | ー |
| 国性爺合戦 (こくせんやかっせん) | 近松門左衛門 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 人形浄瑠璃 | ー | ー |

この4作品の作者が「近松門左衛門」で、ジャンルは「人形浄瑠璃」であることを覚えておこう!
人形浄瑠璃とは、日本の古典芸能の1つです。
人形を操ってストーリーを繰り広げるいわば人形劇です。
現在では「文楽」の名でも知られていますね。
4作品ともよく選択肢になっていますが、よく出題されているのは『曽根崎心中』です。
実際にあった男女の心中事件を元に、男女の愛の美しさを物語にしています。
・近松門左衛門の作品のジャンルは人形浄瑠璃
・近松門左衛門の作品の成立は元禄文化期
井原西鶴の代表作
井原西鶴の作品は、以下の4つがよく出題されます。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 好色一代男 (こうしょくいちだいおとこ) | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (好色物) | ー | ー |
| 好色五人女 (こうしょくごにんおんな) | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (好色物) | ー | ー |
| 日本永代蔵 (にっぽんえいたいぐら) | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (町人物) | ー | ー |
| 世間胸算用 (せけんむねさんよう) | 井原西鶴 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 浮世草紙 (町人物) | ー | ー |

この4作品の作者が「井原西鶴」で、ジャンルは「浮世草紙」であることを覚えておこう!
「浮世草子」とは「娯楽性の高い小説」です。
今で言うと「ラノベ」のようなものでしょうか。
江戸時代当時は「文学」というと「学問を積んだ人のモノ」でした。
「浮世草紙」は一般庶民でもラクに楽しめるように「恋愛などの人間関係」や「身近な生活」を題材にしています。
浮世草子の中にも「好色物」「町人物」のジャンル分けがあります。頻出ではありませんが「浮世草紙」と結びつくようにしておきましょう。
・井原西鶴の作品のジャンルは浮世草紙
・井原西鶴の作品の成立は元禄文化期
松尾芭蕉の代表作
松尾芭蕉の作品は、以下の3つがよく出題されます。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 野ざらし紀行 | 松尾芭蕉 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 俳諧 紀行 | ー | ー |
| 笈の小文 | 松尾芭蕉 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 俳諧 紀行 | ー | ー |
| おくのほそ道 | 松尾芭蕉 | 江戸時代前期 (元禄文化) | 俳諧 紀行 | 北陸・奥州を巡る | ー |

この3作品の作者が「松尾芭蕉」で、ジャンルは「俳諧」「紀行」であることを覚えておこう!
松尾芭蕉は「俳人(=俳句を作る人)」です。
俳句とは「五七五」の17文字で詠むもの。和歌の五七五七七の31文字よりも少ない文字数で表現します。
あとは、季節を表す季語を入れるのもルールです。
上記の3作品は、松尾芭蕉が全国を旅して、その土地や旅の中で感じたことを俳句で表現したものを集めた記録です。
ですので、ジャンルは「俳諧」であり「紀行(=旅日記)」です。
『おくのほそ道』は有名すぎて、あまり問題になっていません。
松尾芭蕉関連の問題では『野ざらし紀行』が圧倒的に出題されています。
・松尾芭蕉の作品のジャンルは俳諧・紀行
・松尾芭蕉の作品の成立は元禄文化期
【元禄文化期の文学】はココが出る!まとめ
「元禄文化期の文学」で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・元禄文化の担い手は「近い松」で覚える
近:近松門左衛門・い:井原西鶴・松:松尾芭蕉
・近松門左衛門の作品は『出世景清』『曾根崎心中』『冥途の飛脚』『国性爺合戦』
・近松門左衛門の作品のジャンルは人形浄瑠璃
・近松門左衛門の作品の成立は元禄文化期
・井原西鶴の作品は『好色一代男』『好色五人女』『日本永代蔵』『世間胸算用』
・井原西鶴の作品のジャンルは浮世草紙
・井原西鶴の作品の成立は元禄文化期
・松尾芭蕉の作品は『野ざらし紀行』『笈の小文』『おくのほそ道』
・松尾芭蕉の作品のジャンルは俳諧・紀行
・松尾芭蕉の作品の成立は元禄文化期
「元禄文化期の文学」の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
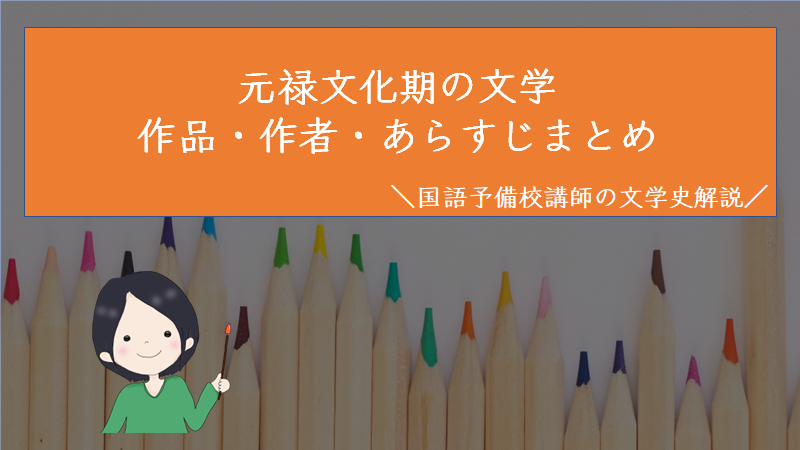
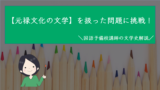


コメント