・『古今和歌集』の基礎知識(撰者・成立年代・特徴)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは『古今和歌集』の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2022年 九州大学
・2020年 駒澤大学
・2019年、2017年 上智大学
ほか
『古今和歌集』の基礎知識 撰者・時代・特徴は?
まずは『古今和歌集』の基礎知識を整理します。
| 作品名 | 撰者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 古今和歌集 (古今集) | 紀貫之 紀友則 凡河内躬恒 壬生忠岑 天皇:醍醐天皇 | 平安初期:『源氏物語』以前の平安時代/最初の勅撰和歌集 | 勅撰和歌集 | 「たおやめぶり」と形容される | 仮名序の作者は紀貫之/代表歌人は六歌仙+α |
では、覚えるポイントをひとつずつ確認していきましょう。
撰者:紀貫之・凡河内躬恒・紀友則・壬生忠岑
『古今和歌集』の撰者は4人。
・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)
・紀友則(きのとものり)
・壬生忠岑(みぶのただみね)
撰者を問われる問題で、答えになるのは「紀貫之」が圧倒的に多いですが、ほかの3人も出題はされています。
成立年代:平安初期
『古今和歌集』の成立年代は平安時代初期の西暦900年頃です。
『古今和歌集』の成立年代を問う問題は大きく2パターンあります。
②『源氏物語』以前に成立した作品であること
①は、他の勅撰和歌集と年代比較した問題が出ます。
詳しくは、勅撰和歌集について解説したページを参照してください。
→【勅撰和歌集】一覧!順番・覚え方は?
②について、『源氏物語』以前に成立した作品はよく問題になります。
詳しくは【年代攻略】『源氏物語』以前の作品まとめにまとめています。こちらも参照してください。
また、撰者の一人である、紀貫之が書いた『土佐日記』と同時期に成立していることも把握しておきましょう。(当然と言えば当然ですね)
ジャンル:勅撰和歌集
「勅撰和歌集」とは、天皇の命令で作られた和歌集のことです。
国家事業として和歌集を作っているということですね。
詳しいことは勅撰和歌集について解説したページを参照してください。
『古今和歌集』の編纂命令を出したのは「醍醐天皇」です。
頻度は高くありませんが、ときどき出題されています。
内容:「たおやめぶり」と形容される
『古今和歌集』の歌風は「たおやめぶり」と表現されます。

「たおやめぶり」ってなに?

直訳すると「女らしい」の意味だよ。
『古今和歌集』の歌風を説明するときに使われるんだ。
『古今和歌集』の時代になると「掛詞・縁語・序詞」などの表現技巧が多用されるようになります。
物事をはっきりと言わない方が優雅で奥ゆかしい!いいね!という風潮に移り変わっていきます。
この状況を「女らしい(=たおやめぶり)」と江戸時代の国学者・賀茂真淵と本居宣長が表現しました。
→国学については【国学とは?】文学作品・作者まとめを参照してください。
ポイント
『古今和歌集』のよく出るポイントを2点紹介します。
- 仮名序の作者は紀貫之
- 代表歌人は六歌仙+α
一つずつ確認しましょう。
仮名序の作者は紀貫之
「仮名序(かなじょ)」とは、『古今和歌集』の最初に書いてある、今でいう「まえがき」のような文章です。
仮名序を書いたのは、撰者の一人である「紀貫之」です。
仮名序には
・素晴らしい歌の基準とは何か?
などが書かれています。
また、仮名序は後世の文学作品に引用されたり、表現の下敷きにされることが多々あります。
「仮名序」の書き出しを紹介します。
【抜粋(読みやすく漢字にしました)】
やまとうた(和歌)は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。
力をも入れずしてあめつち(天地)を動かし、目に見えぬおにかみ(鬼神)をもあはれと思わせ、男女の仲をも和らげ、猛き武士の心をも慰むるは歌なり。
【意訳】
和歌は、人の心を種として、たくさんの言葉になっているのだ。
力を入れずに天地を動かし、目に見えない鬼神をも感動させ、男女の仲をやわらげ、猛き武士の心を慰めるのは歌である。
特に
・「やまとうた(=和歌)は人の心を種として…」
・「鬼神をも感動させる」
この2つの表現は古文の読解問題でもよく見かけます。
代表歌人は撰者4人と六歌仙
『古今和歌集』の代表歌人が問題になることもあります。
覚えておくべきは撰者の4人と六歌仙と呼ばれる6人です。
六歌仙とは、平安時代の歌の名手6人の総称です。
要するに「平安時代初期の歌ウマ☆名人」だと思っておいてください。
その6人とは…
先ほど触れた「仮名序」の中で紀貫之がこの6人の歌風について述べたところがあります。そこから「紀貫之に認められた6人」という風にグループ分けされるようになりました。
問題としてはマニアックですが、ときどき六歌仙を選ぶ問題も出題されますので、細かいところまで対策しておきたい場合は6人の名前も覚えておきましょう。
『古今和歌集』はココが出る!まとめ
『古今和歌集』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『古今和歌集』の撰者は紀貫之・凡河内躬恒・紀友則・壬生忠岑
・『古今和歌集』は最初の勅撰和歌集
・『古今和歌集』は『源氏物語』以前の平安時代に成立
・『古今和歌集』の歌風は「たおやめぶり」と形容される
・『古今和歌集』「仮名序」の作者は紀貫之
・『古今和歌集』の代表歌人は撰者4人と六歌仙
・六歌仙とは「在原業平・小野小町・文屋康秀・僧正遍照・喜撰法師・大友黒主」の総称
『古今和歌集』の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
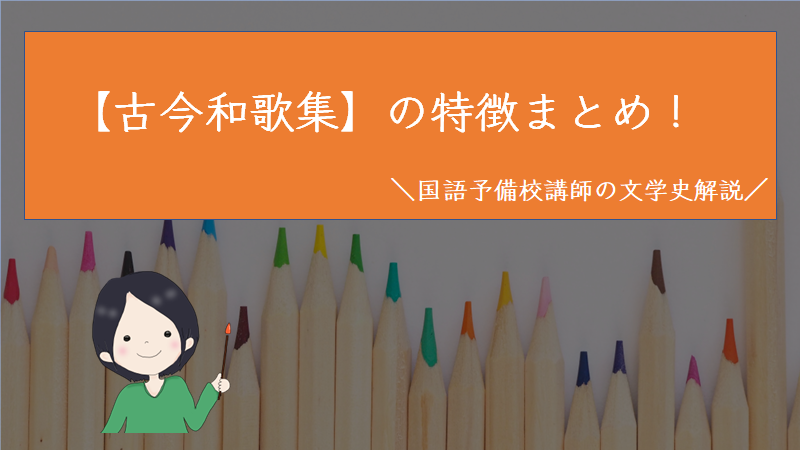
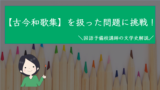


コメント