
ことのは
こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
過去問5年分以上の大学入試の文学史問題を分析した結果から「よく出る問題」だけに絞って出題・解説します。
今回は『風姿花伝』を扱います。
そもそも『風姿花伝』って何だ?問題解ける気がしないぞ?と思った場合は、基礎知識を整理したページを先に読んでから挑戦してみてください。
では、今回の練習問題に挑戦!
問題
問1
『風姿花伝』の作者は誰か。
『風姿花伝』の作者は誰か。
1.上田秋成
2.兼好法師
3.世阿弥
4.本居宣長
問2
次のうち、『風姿花伝』と同じ時代に成立した作品はどれか。
次のうち、『風姿花伝』と同じ時代に成立した作品はどれか。
1.一寸法師
2.今昔物語
3.世間胸算用
4.方丈記
↓
↓
↓(答えが出ます)
↓
↓
答え・解説
問1
『風姿花伝』の作者は誰か。
『風姿花伝』の作者は誰か。
1.上田秋成(雨月物語)
2.兼好法師(徒然草)
3.世阿弥
4.本居宣長(玉勝間・古事記伝など)
単純な一問一答問題でした。
『風姿花伝』の作者は世阿弥です。
・『風姿花伝』の作者は世阿弥
問2
次のうち、『風姿花伝』と同じ時代に成立した作品はどれか。
次のうち、『風姿花伝』と同じ時代に成立した作品はどれか。
1.一寸法師
2.今昔物語(平安時代)
3.世間胸算用(江戸時代)
4.方丈記(鎌倉時代前期)
『風姿花伝』が成立したのは室町時代です。
『一寸法師』が「お伽草紙」というジャンルの室町時代に成立した作品だと知っていれば積極的に選べます。(浦島太郎、酒吞童子なども同じくお伽草紙)
ここでは、2-4の選択肢がそれぞれ室町時代ではない、ということが分かることも大切です。
『風姿花伝』が室町時代だと分かっていれば、消去法でも選べる問題でした。
・『風姿花伝』の成立年代は室町時代
『風姿花伝』はココが出る!まとめ
『風姿花伝』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『風姿花伝』の作者は世阿弥
・『風姿花伝』の成立年代は室町時代
・『風姿花伝』のジャンルは能の理論書(能楽書)

ことのは
これさえ覚えれば、『風姿花伝』関連の大学受験文学史問題の9割は解ける!
今回はここまで。
定着させるために、繰り返し問題を解いてくださいね。
『風姿花伝』の基礎知識を確認しておきたい場合はこちらのページを確認してください。

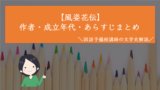


コメント