・『万葉集』の基礎知識(撰者・成立年代・代表歌人)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは『万葉集』の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2022年 青山学院大学(文)
・2018年 熊本大学
ほか
『万葉集』の基礎知識 撰者・時代・特徴は?
まずは『万葉集』の基礎知識を整理します。
| 作品名 | 撰者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 万葉集 | 大伴家持 (諸説あり) | 奈良時代 (最古の和歌集) | 和歌集 (勅撰和歌集ではない) | さまざまな身分の人の和歌を収録/歌風は「ますらをぶり」と形容される | 代表歌人は額田王・天智天皇・柿本人麻呂・山部赤人 |
では、覚えるポイントをひとつずつ確認していきましょう。
撰者:大伴家持
『万葉集』の撰者は「大伴家持(おおとものやかもち)」です。
『万葉集』には20巻4500首もの和歌が収められています。
和歌の作者はたくさんいますが、どの和歌を掲載するかを選んだのは撰者である大伴家持です。
実は『万葉集』の撰者には諸説あるのですが、文学史の問題では「大伴家持」と答えておきましょう。
成立年代:奈良時代
『万葉集』の成立年代は「奈良時代」です。
日本で現存する最古の和歌集です。
「最古の和歌集」は『万葉集』のキーワードです。覚えておきましょう。
ジャンル:和歌集
『万葉集』は、たくさんの人の和歌を収録した「和歌集」です。
内容
『万葉集』の特徴として知っておくべきことは2点。
- さまざまな身分の人の和歌を収録
- 歌風は「ますらをぶり」と形容される
一つずつ確認してみましょう。
さまざまな身分の人の和歌を収録

『万葉集』って4500首も収録されているんだね!
誰がそんなにたくさんの和歌を詠んだの?

同じ人が4500首詠んだわけじゃないよ。
いろんな身分の人の和歌を集めてきた和歌集なんだ。
万葉集の特徴は【とにかくいろんな人の和歌が収録されている】こと。
『万葉集』は性別・出身地や居住地・身分など問わずに、さまざまな人の和歌が収録されています。
天皇や貴族はもちろん、
「防人歌(さきもりうた)」という、九州を警備する役職の人の歌や、
「詠み人知らず」という、そもそも誰が詠んだのかわからない和歌もあります。
平安時代以降に作られた貴族中心の和歌集とは違いますね。
歌風は「ますらをぶり」と形容される
奈良時代は、まだ和歌が発達段階だったこともあり、平安時代ほど和歌の技術は発展していませんでした。
技巧を凝らしすぎない、素直・素朴でわかりやすい和歌が多いです。
この「素朴」な特徴をとらえて、のちに江戸時代の学者(本居宣長)が「ますらをぶり(男らしい)」の歌風だと表現しました。
→国学については【国学とは?】文学作品・作者まとめを参照してください。
『万葉集』は成立した後、再び注目を浴びるのは約1000年後の江戸時代です。
21世紀を生きるわれわれからすると江戸時代も「歴史」ですが、江戸時代の人にとっても、『万葉集』は古典でした。1000年前の言語を解読するのはかなり骨の折れる作業で、現代でもまだ読み方が分かっていない部分もたくさん残っています。
ポイント:代表歌人は額田王・天智天皇・柿本人麻呂・山部赤人
『万葉集』の代表歌人を問われることも多いです。
有名な人・よく出題される人をまとめます。
- 天智天皇
- 天智天皇(中大兄皇子)と言えば「大化の改新の人」「百人一首の最初の人」です。
日本史の知識からも奈良時代の人であることは推測できそうですね。 - 額田王
- 額田王(ぬかたのおおきみ)は天智天皇の妻です。
- 柿本人麻呂・山部赤人
- 柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)と山部赤人(やまべのあかひと)は、歌聖(かせい=和歌がうまい人)として後の世まで尊敬され、名前が残っています。
百人一首でも「3首目:柿本人麻呂 4首目:山部赤人」で序盤に収録されているます。覚えた人も多いかな? - 山上憶良
- 山上憶良(やまのうえのおくら)は、奈良時代の歌人です。日本史で『貧窮問答歌』の作者とも習いますね。
- 大伴家持
- 大伴家持は撰者というだけでなく、もちろん和歌も収録されています。
実は、4500首のうち473首は大伴家持の和歌です。(まさかの1割超え)
『万葉集』はココが出る!まとめ
『万葉集』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『万葉集』の撰者は大伴家持
・『万葉集』は奈良時代に成立
・『万葉集』は日本最古の和歌集
・『万葉集』はさまざまな身分の人の和歌を収録
・『万葉集』の歌風は「ますらをぶり」と形容される
・『万葉集』の代表歌人は額田王・天智天皇・柿本人麻呂・山部赤人・山上憶良
『万葉集』の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
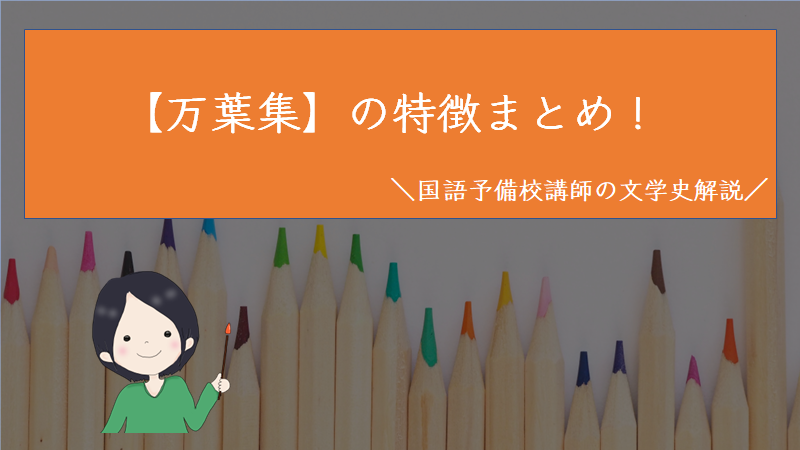

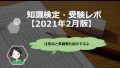

コメント