・「勅撰和歌集」の基礎知識(順番・覚え方)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは「勅撰和歌集」の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2022年 明治大学
・2018年 関西学院大学
ほか
「勅撰和歌集」一覧 基礎知識まとめ
まずは「勅撰和歌集」の基礎知識を一覧表で整理します。
| 作品名 | 撰者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 古今和歌集 | 紀貫之 紀友則 凡河内躬恒 壬生忠岑 天皇:醍醐天皇 | 平安初期:『源氏物語』以前の平安時代/最初の勅撰和歌集 | 勅撰和歌集 | 「たおやめぶり」と形容される | 仮名序の作者は紀貫之/代表歌人は六歌仙+α |
| 後撰和歌集 | (梨壺の五人) | ★ | 勅撰和歌集 | – | – |
| 拾遺和歌集 | – | ★(1000年頃) | 勅撰和歌集 | – | – |
| 後拾遺和歌集 | – | ★ | 勅撰和歌集 | – | – |
| 金葉和歌集 | (源俊頼) | ★ | 勅撰和歌集 | – | – |
| 詞花和歌集 | – | ★ | 勅撰和歌集 | – | – |
| 千載和歌集 | 藤原俊成 | ★ | 勅撰和歌集 | – | 俊成は『古来風体抄』の作者でもある |
| 新古今和歌集 | 藤原定家 (代表者) 天皇:後鳥羽院 | 鎌倉時代初期 | 勅撰和歌集 | 幽玄・有心・幻想的 | 代表歌人は俊成・西行/定家の著作と関連させておく |

え…こんなの覚えられない…
さようなら…

ちょっと待って!
出題されるところはそんなに多くないから、もうちょっと頑張ろう!
表の数に圧倒されてしまった人もいるかもしれませんが、勅撰和歌集をテーマにした問題では出題されるところがある程度決まっています。
このページのもう少し下の部分で覚えるべきポイントに絞って紹介します。
その前に「勅撰和歌集」とは何か?という概要を説明しておきますね。
勅撰和歌集とは?
「勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう)」とは、天皇の命令で作られた和歌集のことです。
天皇自身が和歌を選ぶ場合もありますし、有名な歌人に命令を出して選ばせることもあります。
「勅」は「天皇の」という意味です。
(ex:「勅命」=「天皇の命令」、「勅許」=「天皇のおゆるし」)
「勅撰和歌集」は最初に作られた『古今和歌集』から始まり、全部で21作品ありますが、大学受験文学史で出題されるのは、最初の8作品(上の表)ばかりです。
『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの8作品をまとめて「八代集」と呼びます。
また、天皇の命令で作られた「公」の和歌集を勅撰和歌集と言うのに対して、個人で作る和歌集のことを「私家集」と言います。
「勅撰和歌集」よく出るポイント
「勅撰和歌集」について出題される場合は、ある程度問題のパターンは決まっています。
だいたいこの4ポイントです。
①②については、それぞれを紹介したページを用意していますので、参照してください。
このページでは③④をメインに紹介していきます。
八代集の成立順は?ゴロ合わせも紹介!
「勅撰和歌集」関連では「成立順」を問う問題が頻出です。
成立順問題の対策のために覚えておいてほしいポイントは2点。
・間の6作品の成立順は「五千円拾ったあと、禁止せん」(ごせんえん ひろった あと きん し せん)」で覚える
まず一つ目。
『古今和歌集』と『新古今和歌集』の成立年代は単体でもよく問題になります。
名前を見る限り『古今和歌集』→『新古今和歌集』の順番であることは見当がつきます。
八代集最後:新古今和歌集:鎌倉初期(約1200年)
成立年代には約300年の隔たりがあります。(年号は覚えなくてもいいです)
最初は『古今和歌集』で平安初期・最後は『新古今和歌集』で鎌倉初期と、起点と終点の時代感覚は持っておきましょう。
二つ目。
間の6作品については、『千載和歌集』を除いて成立年代を問う問題しか出題されません。覚えるのも大変だと思いますので、ゴロ合わせで乗り切りましょう。
ごせん(えん)→後撰和歌集
拾った→拾遺和歌集
あと→後拾遺和歌集
きん→金葉和歌集
し→詞花和歌集
せん→千載和歌集
この2ポイントをまとめると
要するに…↓
→ごせん(後撰和歌集)
→拾った(拾遺和歌集)
→あと(拾遺和歌集)
→きん(金葉和歌集)
→し(詞花和歌集)
→せん(千載和歌集)
→新古今:最後

分解すると覚えられそうな気がしてこない?
『千載和歌集』の撰者は藤原俊成
『新古今和歌集』の直前に成立した勅撰和歌集、『千載和歌集』の撰者は「藤原俊成(ふじわらしゅんぜい)」です。
間に挟まっている6作品に関する問題は成立順を覚えておけばいいのですが、『千載和歌集』だけは撰者も問われることがありますので、覚えておきましょう。
ちなみに『千載和歌集』の撰者:藤原俊成(父)→『新古今和歌集』の撰者:藤原定家(子)という関係です。
さらに藤原俊成は『新古今和歌集』の代表歌人でもありますので、『千載和歌集』と『新古今和歌集』はかなり近い年代に成立したことも推測できるようになりますね。
また、藤原俊成は『古来風体抄』という歌論書も書いています。
少しマニアックですが、ときどき問題になっているので余力があれば覚えておきましょう。
「勅撰和歌集」はココが出る!まとめ
「勅撰和歌集」で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・八代集の成立年代は『古今和歌集』(平安初期)→6作品→『新古今和歌集』(鎌倉初期)
・間の6作品の成立順は「五千円拾ったあと、禁止せん」(ごせんえん ひろった あと きん し せん)」で覚える
・『千載和歌集』の撰者は藤原俊成
・『古来風体抄』は藤原俊成が書いた歌論書
「勅撰和歌集」の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
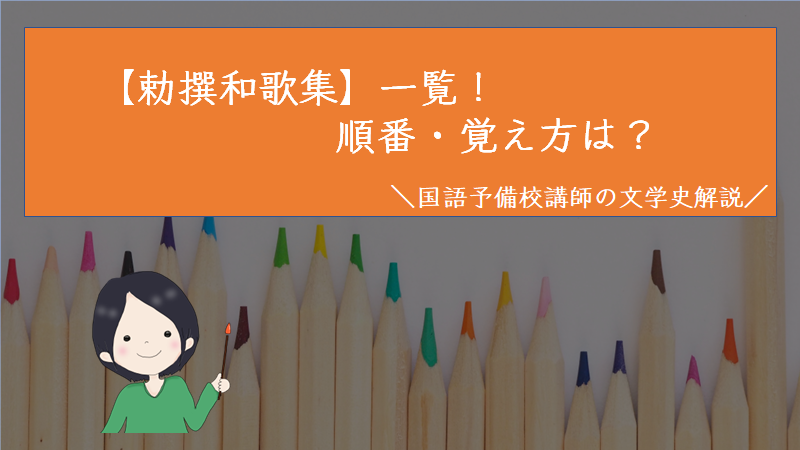
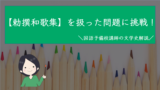


コメント