・『徒然草』の基礎知識(作者・成立年代・あらすじ)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは『徒然草』の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2021年 琉球大学
・2016年 埼玉大学
ほか
『徒然草』の基礎知識 作者・成立年代・ジャンルは?
まずは『徒然草』(つれづれぐさ)の基礎知識を整理します。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 徒然草 | 兼好法師 | 鎌倉時代後期 | 随筆 | 兼好法師が感じたことの記録 | ー |
では、覚えるポイントをひとつずつ確認していきましょう。
作者:兼好法師
『徒然草』の作者は兼好法師(けんこうほうし)です。
「吉田兼好」とか「卜部兼好」とか表記されていることもあります。研究者の中でも分かれているところなので、「兼好」を覚えておけば対応できるはずです。
成立年代:鎌倉時代後期
『徒然草』の成立年代は鎌倉時代後期です。
『徒然草』は日本三大随筆の一つです。
同じく日本三大随筆に分類される『方丈記』も鎌倉時代の成立なので、『方丈記』・『徒然草』どっちが先に成立したのかを把握するために鎌倉時代「後期」のところまで覚えておきましょう。
成立年代を表にするとこんな感じ↓
随筆という同じジャンルで並び替えをする問題も見かけますので、整理しておきましょう。
ジャンル:随筆
『徒然草』のジャンルは「随筆」です。
随筆とは、「他者に読まれる前提の日記」です。
自分の意見とか、感じたこと・思ったことを文章にしたものです。「エッセイ」ともいいます。
内容:兼好法師が感じたことの記録
『徒然草』は作者:兼好法師が経験したことや、そこから感じたことを記録していく文章です。
つれづれなるままに、日暮らし、硯(すずり)に向かひて、心にうつりゆくよしなしことを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
(意訳)
退屈に任せて、一日中、硯に向かって、心に浮かんでくる取るに足らないことを、とりとめもなく書きつけていくと、不思議なくらい熱中して変な気分になってくる。
作者:兼好法師が、心に浮かんだことを取りとめもなく記録していく、という言葉から『徒然草』は始まります。
教科書にも載っている『仁和寺にある法師』『猫また』『高名の木登り』などはまさに、「作者の経験したこと」+「感じたこと」で構成されている文章です。
『徒然草』はココが出る!まとめ
『徒然草』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『徒然草』の作者は兼好法師
・『徒然草』の成立年代は鎌倉時代後期
・『徒然草』のジャンルは随筆
・日本三大随筆とは『枕草子』『方丈記』『徒然草』
・『徒然草』の内容は兼好法師が感じたことの記録
『徒然草』の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
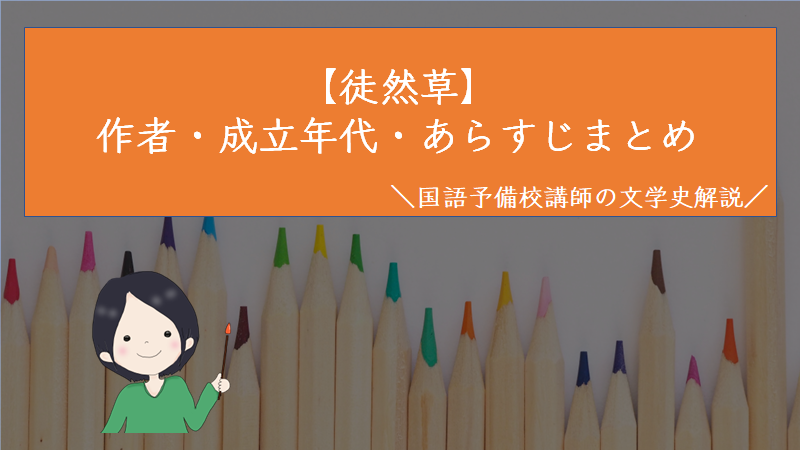
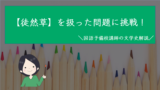


コメント