・平安時代に成立した作品の基礎知識
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは「平安時代に成立した作品」の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2022年 龍谷大学
・2020年 早稲田大学
・2020年 九州大学
ほか
【平安時代に成立した作品】まとめ
頻出作品はそれぞれのページでまとめているので参照してください。
・【作り物語】の代表作3つまとめ
・【土佐日記】作者・成立年代・あらすじは?
・【古今和歌集】の撰者・時代・特徴は?
・【蜻蛉日記】作者・成立年代・あらすじは?
・【枕草子】作者・成立年代・あらすじは?
・【紫式部】の作品・成立年代・あらすじは?
・【更級日記】作者・成立年代・あらすじは?
・【歴史物語】一覧!順番・覚え方は?
当ページでは、上記テーマに収まりきらなかった作品を紹介します。
『源氏物語』以降に成立した作り物語 3作品
『源氏物語』以降の平安時代に成立した作り物語として、『狭衣物語』『堤中納言物語』『とりかへばや物語』の3作品紹介します。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 狭衣物語 | ー | 『源氏物語』以降の平安時代 | 作り物語 | 狭衣大将の恋愛遍歴 | 『源氏物語』の影響を受ける |
| とりかへばや物語 | ー | 『源氏物語』以降の平安時代 | 作り物語 | 性別を入れ替えて生活する姉と弟の話 | ー |
| 堤中納言物語 | ー | 『源氏物語』以降の平安時代 | 作り物語 | 短編集 | 『虫めづる姫君』が有名 |
作り物語とは「虚構の物語」つまり現代でいう小説のことです。
『源氏物語』以前に成立した作り物語は別ページで紹介しています。
→【年代攻略】『源氏物語』以前の作品まとめ
『源氏物語』をきっかけに、作り物語がどんどん作られるようになります。
狭衣物語
『狭衣物語』(さごろもものがたり)は、本命の女性への恋が報われなかった狭衣大将という人が、本命の女性への恋が報われず、いろんな女性と恋愛する話です。

なんか聞いたことあるストーリーかも?

そうだね、『源氏物語』とほぼ同じ。
『源氏物語』は、光源氏という貴公子が本命の女性(藤壺)への恋が実らず、いろんな女性と恋愛する話でした。
『狭衣物語』は、『源氏物語』の影響を多大に受けています。
とりかへばや物語
『とりかへばや物語』は男っぽい姉と、女っぽい弟が、男女逆転生活を送る物語です。
姉は男として宮中に仕え、弟は女として生活を送るうちに、お互いに結婚の話が出てきて…どうする?!的なドタバタコメディです。
『ざ・ちぇんじ』という小説(のちにマンガ化)は『とりかへばや物語』を現代風にアレンジした作品です。
堤中納言物語
『堤中納言物語』(つつみちゅうなごんものがたり)は10個の作品が入っている短編集です。
有名なのは『虫愛づる姫君』という作品。
虫が大好きな高貴なお姫様がいて、虫を飼ったり、さなぎを集めて育てたりして周囲の女房(=お手伝い係)をビビらせていました。せっかくの求婚も断ってしまって…という当時の基準からすると、ちょっと変わったお姫様の話です。
紹介した3作品は、全て作者が不明です。
『源氏物語』以降に成立した「作り物語」という2ポイントを押さえておきましょう。
・『狭衣物語』『とりかげばや物語』『堤中納言物語』のジャンルは作り物語
・『とりかへばや物語』は男女逆転物語
和漢朗詠集
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 和漢朗詠集 | 藤原公任 | 平安時代 (約1000年) | 歌集 | 文化芸術の天才が集めた歌集 | ー |
『和漢朗詠集』(わかんろうえいしゅう)は、藤原公任(ふじわらきんとう)が選んだ歌集です。”朗詠”とは、声に出して歌を読むこと。この作品は、言うなれば”声に出して読みたい歌集”です。
藤原公任は作文(漢文)、和歌、管弦(楽器)そして書などの文化・芸術の才に恵まれた人でした。(詳しくは『大鏡』三船の才で検索!)
当時の芸術の名手が「良い」とした和歌を集めた作品です。
また、藤原公任は、藤原道長と同時代の人です。大学受験文学史の基準となる約1000年(和泉式部・清少納言・紫式部)の人だとイメージを持っておきましょう。
・『和漢朗詠集』の成立は平安時代(約1000年)
・『和漢朗詠集』のジャンルは歌集
梁塵秘抄
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 梁塵秘抄 | 後白河法皇 | 平安時代末期 | 歌謡集 | 「今様」を集める | ー |
『梁塵秘抄』(梁塵秘抄)は、後白河(ごしらかわ)法皇が編集した歌謡集です。
テキストによっては、「後白河天皇」「後白河院」と書いてある場合もありますが、全て同じ人です。
(ちなみに「院」「法皇」は、元・天皇だった人のこと)
後白河法皇は、どうやら五七五七七の和歌が得意ではなかったようで(ウワサです)、庶民の流行だった「今様」という、和歌とは違ったスタイルの歌がお気に入りだったようです。やり過ぎて喉を痛めたことが二度もあったらしい。
この「今様」が収められたのが『梁塵秘抄』です。
後白河法皇が生きたのは、平安時代末期~鎌倉時代にかけてです。
日本史の知識と照らし合わせると、平家が台頭してきて、源平合戦が起こり、最終的に源氏が鎌倉幕府を起こした時代です。
武士が力を持つ時代でありながら、様々な策を使い、朝廷の権力を保つために上手く立ち回ります。
日本史を勉強していれば、後白河法皇は「院政」でもおなじみですね。(※文学史では出ません)
・『梁塵秘抄』の成立は平安時代末期
・『梁塵秘抄』は「今様」を収録した歌謡集
歌論
「歌論」とは、和歌の批評をした文章です。
どういう和歌が良くて、和歌とはどういったものなのかについて、筆者の考えを記した評論文です。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 俊頼髄脳 | 源俊頼 | 平安時代末期 | 歌論 | 和歌とは何かを述べる | ー |
| 袋草紙 | (藤原清輔) | 平安時代末期 | 歌論 | 和歌とは何かを述べる | ー |
ただ、今回挙げた『俊頼髄脳』『袋草紙』は「平安時代後期」成立の「歌論」だと覚えておくだけでOKです。
内容まで問われることはありません。
【平安時代に成立した作品】はココが出る!まとめ
【平安時代に成立した作品】で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『狭衣物語』『とりかげばや物語』『堤中納言物語』は『源氏物語』以降の平安時代に成立
・『狭衣物語』『とりかげばや物語』『堤中納言物語』のジャンルは作り物語
・『とりかへばや物語』は男女逆転物語
・『和漢朗詠集』の作者は藤原公任
・『和漢朗詠集』の成立は平安時代(約1000年)
・『和漢朗詠集』のジャンルは歌集
・『梁塵秘抄』の作者は後白河法皇
・『梁塵秘抄』の成立は平安時代末期
・『梁塵秘抄』は「今様」を収録した歌謡集
・『俊頼髄脳』『袋草紙』は平安時代後期成立の歌論
【平安時代に成立した作品】の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
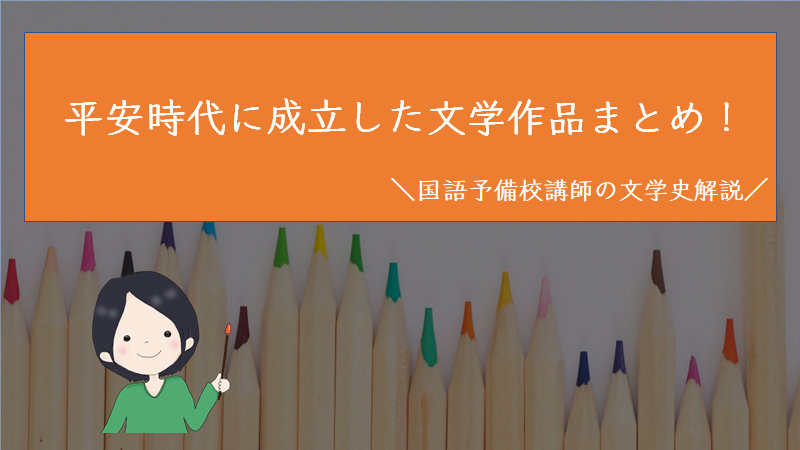
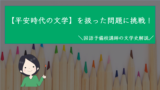


コメント