・『蜻蛉日記』の基礎知識(作者・成立年代・あらすじ)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは『蜻蛉日記』の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2021年 香川大学
・2021年 福岡教育大学
ほか
『蜻蛉日記』の基礎知識 作者・成立年代・ジャンルは?
まずは『蜻蛉日記』(かげろうにっき)の基礎知識を整理します。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 蜻蛉日記 | 藤原道綱母 | 『源氏物語』以前の平安時代 | 日記 | 夫・兼家の浮気を嘆く日記 | 『更級日記』と区別する |
では、覚えるポイントをひとつずつ確認していきましょう。
作者:藤原道綱母
作者は藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)です。
当時の女性の本名は、両親や配偶者など、近しい人にしか明かしませんでした。
よって、藤原道綱母にも「〇子」のような名前があったと思われますが、「藤原道綱という人のお母さん」という呼び名以外には現代には残っていません。
(現代の「〇〇さんのお母さん」「部長の奥さま」のような呼びかけ方と同じですね)
『蜻蛉日記』の作者はよく問題になります。
なぜなら『更級日記』と混同しやすいから!
『更級日記』ー菅原孝標女
どちらも『〇〇日記』、「〇原」、「母or女」など、なんとなく共通点が多い。
※『更級日記』の詳細は【更級日記】作者・成立年代・あらすじは?を参照してください。
よく問題になっていますので、しっかり覚えておきましょう。覚え方は下の「ポイント」で紹介します。
成立年代:『源氏物語』以前の平安時代
『蜻蛉日記』の成立年代は『源氏物語』以前の平安時代です。
成立年代が問題になるときは、『源氏物語』との前後関係で聞かれることが多いので、押さえておきましょう。
『源氏物語』以前の平安時代、これだけでOK!
※『源氏物語』以前に成立した作品はよく問題になりますので、【年代攻略】『源氏物語』以前の作品まとめにまとめています。参考にしてください。
ジャンル:日記
『更級日記』のジャンルは「日記」です。
タイトルに「日記」と入っているので、ジャンルが問題になることはありません。
内容:夫の浮気を嘆く日記
『蜻蛉日記』の主な内容は「夫・藤原兼家の浮気に対するグチ」です。
平安時代において「一夫多妻」は悪いことではありませんでした。ただ、悪いことではないからと言って、受け入れられるかはまた別の話です。
藤原道綱母は「日本三大美人」と言われるほどの美貌の持ち主だったそうです。いろんな男の人から求婚されていたようですが、最終的に結婚したのは「藤原兼家」という男。あの藤原道長の父です。
兼家が猛アタックに押される形で結婚したようです。
最初の方こそ幸せに暮らしていたようですが、気の多い兼家は浮気を繰り返します。
道綱母は放っておかれるようになり悔しい思いをするように。
【蜻蛉日記の有名な部分】
いかに久しき ものとかは知る
(意訳)
嘆きながら、そしてあなたを思いながら夜を過ごしているの。
そんな夜がどれだけ長いのかご存じ?いや、知らないでしょう?
百人一首にも入っているこの和歌。
ある日、浮気を繰り返している兼家が久しぶりに道綱母のところに来てくれた!
それはそれで嬉しいけれど、寂しい思いをしていたことを知ってほしいと思い、家の扉をすぐに開けずにこの和歌を詠みかけ「拗ねているアピール」をします。
道綱母の想定としては

そんなこと言わずに開けてくれよ~お前に会いたくて来たんだからさ~
的なことを言ってほしかったのだと思いますが、現実はこう。

開けてくれないなら別の女のところへ行くか
さすがに藤原道綱母が気の毒です。
こんな風な兼家との攻防戦、そして息子の道綱の成長などが『蜻蛉日記』には綴られています。

自分のことを気にかけてほしいのに素直に言えないところや、浮気相手に対する嫉妬など、いわゆる「女」の感情が赤裸々に、ストレートに書かれていてとてもおもしろい
ただ、人に読ませることを前提としていないので、
(まさか1000年度に入試問題にされるとは思わない)
主語が取りづらく、読解問題としては難しい部類に入ります。
大まかなあらすじや背景知識などを知っておくと有利に進められますので、ぜひ知っておきましょう!
ポイント
『蜻蛉日記』関連の問題でポイントになるのは、『更級日記』と区別をつけること。
作者を紹介したときにも触れましたが、『蜻蛉日記』と『更級日記』は共通点が多く混同しがちです。ただし、間違えやすいということは問題にもなりやすいということ!
| 源氏以前 | 源氏以降 | 前→後 |
| 蜻蛉日記 | 更級日記 | かげろう→さらしな |
| 藤原道綱母 | 菅原孝標女 | 母→女(むすめ) |
この2作品は成立順も大切なので、
・「かげろう→さらしな」の五十音順
・「母→女(むすめ)」の順
と覚えておきましょう。
『蜻蛉日記』はココが出る!まとめ
『蜻蛉日記』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『蜻蛉日記』の作者は藤原道綱母
・『蜻蛉日記』は『源氏物語』以前の平安時代に成立
・『蜻蛉日記』は夫の浮気を嘆く日記
・『蜻蛉日記』と『更級日記』を区別する問題はよく出るので区別をつけておく
『蜻蛉日記』の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
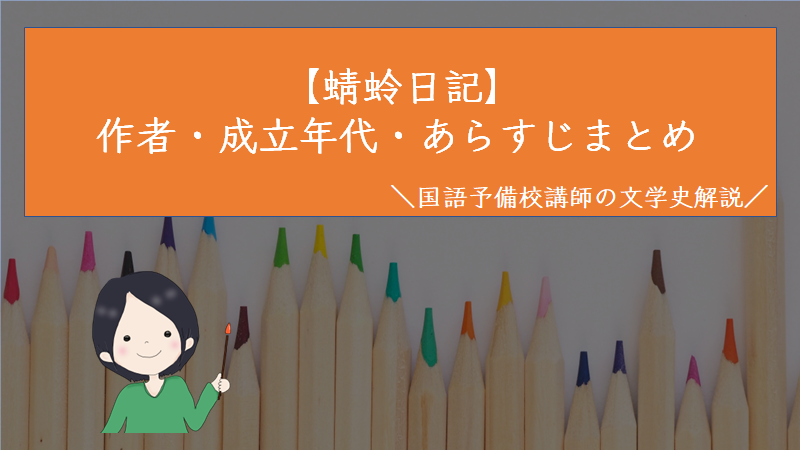
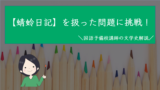


コメント