・「歴史物語」の基礎知識(作品・成立年代・特徴)
・文学史対策のために覚えるポイント
を解説します!

こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
日本文学作品はたくさんありますが、大学入試問題で出題される作品や問題には偏りがあります。国語予備校講師が、過去問5年分以上分析した結果から「よく出るポイント」だけに絞って解説しています。
このページは「歴史物語」の文学史の知識がほぼカバーできるように作っています。知識整理にお役立てください。
・2021年 九州大学
・2019年 学習院大学
・2017年 法政大学
ほか
「歴史物語」一覧 基礎知識まとめ
まずは「歴史物語」の基礎知識を一覧表で整理します。
| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容 | ポイント |
| 栄花物語 (栄華物語) | 赤染衛門? | 平安時代 | 歴史物語 | 藤原道長の栄華 | 編年体 |
| 大鏡 | – | 平安時代 | 歴史物語 | 藤原道長の栄華/ 大宅世継と夏山繁樹の語り | 紀伝体 |
| 今鏡 | – | 平安時代 | 歴史物語 | – | – |
| 水鏡 | – | 鎌倉時代 | 歴史物語 | – | – |
| 増鏡 | – | 南北朝時代 | 歴史物語 | – | – |
覚えるべきポイントは下のポイントの章で確認していきます。
その前に「歴史物語」とは何か?という概要を説明しておきますね。
歴史物語とは?
歴史物語とは「歴史」を「物語風」に書いたものです。
歴史上の出来事や人物を題材にして書いた物語のことです。
あくまで題材にしただけなので、史実そのものではありません。今で言うと大河ドラマのようなものでしょうか。
実際にあった出来事を基にして、読んでいておもしろいくらいのエンタメ性を出したものです。
もちろん100%ウソではないでしょうが、かなり「盛っている」部分はあるはずです。
歴史物語には「ほんまかいな」と思う話も多々収録されています。
「歴史物語」よく出るポイント
「歴史物語」について出題される場合は、ある程度問題のパターンは決まっています。
- 歴史物語の成立順
- 『栄花物語』と『大鏡』の比較
それぞれのポイントについて紹介していきます。
歴史物語の成立順
歴史物語関連の問題では、ジャンル・成立順を問う問題が圧倒的に多いです。
歴史物語に分類される作品はたくさんありますが、大学受験文学史で覚えるべき作品は5つだけ!
ゴロ合わせで覚えてしまいましょう!
はな:栄花物語(栄華物語とも書く):平安中期
だい:大鏡(おおかがみ):平安中期
こん:今鏡(いまかがみ):平安後期
みず:水鏡(みずかがみ):鎌倉初期
まし:増鏡(ますかがみ):南北朝時代
成立順も【はなだいこんみずまし】の順番です。
便利なゴロ合わせですね。
「鏡」とは、歴史をうつす「鏡」の意味があり、後半の4つはまとめて「鏡もの」とか「四鏡(しきょう)」と呼ぶこともあります。
『栄花物語』と『大鏡』の比較
『栄花物語』と『大鏡』は、扱っている内容も成立年代もほぼ同じなので比較した問題が出題されます。
それぞれの共通点と相違点をまとめます。
- 『栄花物語』は編年体・『大鏡』は紀伝体
- 『大鏡』には大宅世継と夏山繁樹という「語り手」がいる
- 『栄花物語』も『大鏡』も藤原道長の栄華を扱っている
『栄花物語』は編年体、『大鏡』は紀伝体
同じ歴史物語でも『栄花物語』と『大鏡』では歴史の描き方が違います。
『大鏡』→紀伝体:出来事や人物に焦点を当てて記録
編年体は出来事を年代順に記録していく方法です。
歴史の教科書のように「〇〇年に□□がありました…次の〇〇年に□□が起こりました…」と記録していきます。
【「年」を基準にして歴史を「編」集する】方法と覚えておいてください。
編年体のメリットは【時代の流れが把握しやすい】、デメリットは【出来事の因果関係がわかりにくい】ところです。
編年体は日本史のイメージ。
日本という国について昔から今までの歴史を時代順に勉強していきますよね。
紀伝体は出来事や人物に焦点を当てて記録していく方法です。
『大鏡』はAさんのエピソード→Bさんのエピソード→Cさんのエピソード…と、人のエピソードを順番に語り、話が進んでいきます。
【伝】記方式だと覚えておいてください。
紀伝体のメリットは編年体と全く逆で、メリットは【出来事の因果関係がわかりやすい】、デメリットは【それぞれのエピソードの時代の前後関係がわかりにくい】ところです。
紀伝体は世界史のイメージ。
まずはエジプトの歴史を勉強して→次に中国の歴史を勉強して→ヨーロッパの歴史の勉強をして…という順番で勉強していきますね。
『大鏡』には大宅世継と夏山繁樹という「語り手」がいる
『栄花物語』は歴史の教科書のように、出来事が淡々と羅列されていくのに対し、『大鏡』には「語り」がいます。
『大鏡』の最初は「雲林院の菩提講」という場面からスタートします。
↓
ありがたいお話が始まるまでは、学校の休み時間のように久しぶりに会う友人とおしゃべり
↓
聴衆の中で大宅世継(180歳)と夏山繁樹(170歳)というおじいちゃんが出会う
↓
年齢が近く、昔の思い出話ができそうな人に会えてうれしい!と、意気投合
(確かに180年前の思い出話に付き合える人はいない)
↓
おじいちゃんが思い出話をするという設定で歴史語りを始める
単に歴史を記述するだけでなく、老人2人が見てきたこととして歴史が語られます。
『栄花物語』も『大鏡』も藤原道長の栄華を扱っている
『栄花物語』も『大鏡』も、メインテーマは「藤原道長の栄華」です。
たくさんの歴史上の出来事を扱っていますが、ページ数を割いて書かれているのは、藤原道長についてです。
上の章でみたように『大鏡』では2人の「語り手」がいます。語り手がそれぞれの出来事についてコメントをしたり、感想を述べたりする場面も書かれています。
このことから『大鏡』では「藤原道長の栄華に対して、批判的」と言われることもあります。
(実際のところは、あまり道長にネガティブな評価をしている印象はありません)
「歴史物語」はココが出る!まとめ
「歴史物語」で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・「歴史物語」に分類されるのは『栄花物語』『大鏡』『今鏡』『水鏡』『増鏡』
・「歴史物語」の成立順は「はな→だい→こん→みず→まし」の順
・『栄花物語』は編年体・『大鏡』は紀伝体
・『大鏡』には大宅世継と夏山繁樹という「語り手」がいる
・『栄花物語』も『大鏡』も藤原道長の栄華を扱っている
「歴史物語」の基礎知識の確認はここまで。
お疲れさまでした!
練習問題も準備していますので、知識が定着しているか確認してみましょう↓
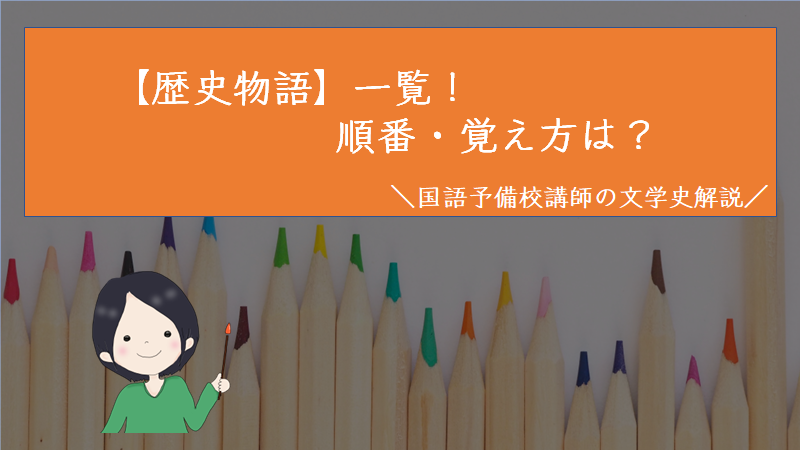
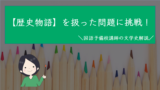


コメント