
こんにちは!
国語予備校講師のことのはです!
過去問5年分以上の大学入試の文学史問題を分析した結果から「よく出る問題」だけに絞って出題・解説します。
今回は『新古今和歌集』を扱います。
そもそも『新古今和歌集』って何だ?問題解ける気がしないぞ?と思った場合は、基礎知識を整理したページを先に読んでから挑戦してみてください。
では、今回の練習問題に挑戦!
問題
『新古今和歌集』の撰者は誰か。
1.紀貫之
2.藤原俊成
3.藤原定家
4.源俊頼
『新古今和歌集』の代表歌人で『千載和歌集』の撰者でもある歌人は誰か。
1.藤原俊成
2.慈円
3.藤原公任
4.西行
1.金槐和歌集
2.山家集
3.無名抄
4.小倉百人一首
↓
↓
↓(答えが出ます)
↓
↓
答え・解説
『新古今和歌集』の撰者は誰か。
1.紀貫之(古今和歌集)
2.藤原俊成(千載和歌集)
3.藤原定家
4.源俊頼
『新古今和歌集』の撰者は「藤原定家」です。
『古今和歌集』の撰者「紀貫之」と区別をつけておきましょう。
『新古今和歌集』の代表歌人で『千載和歌集』の撰者でもある歌人は誰か。
1.藤原俊成
2.慈円
3.藤原公任
4.西行
『新古今和歌集』の代表歌人は「藤原俊成と西行」を問われることが多いです。
さらに『千載和歌集』の撰者で絞ると「藤原俊成」です。
※詳しくは【勅撰和歌集】一覧!順番・覚え方は?を参照してください。
・『千載和歌集』の撰者は藤原俊成
1.金槐和歌集(源実朝)
2.山家集(西行)
3.無名抄(鴨長明)
4.小倉百人一首
『新古今和歌集』の撰者は藤原定家です。
藤原定家は『小倉百人一首』の撰者でもあります。
撰者つながりで藤原定家の著作を問う問題もよく見かけますので、タイトルを知っておきましょう。
・藤原定家の著作は『小倉百人一首』・『松浦宮物語』・『明月記』・『拾遺愚草』
『新古今和歌集』はココが出る!まとめ
『新古今和歌集』で覚えるべきポイントをまとめます。
チェックポイント
・『新古今和歌集』の撰者は藤原定家
・『新古今和歌集』の成立年代は鎌倉時代初期
・『新古今和歌集』のジャンルは勅撰和歌集
・『新古今和歌集』の特徴は「幽玄・有心・幻想的」
・『新古今和歌集』の代表歌人は藤原俊成・西行
・藤原定家の著作は『小倉百人一首』・『松浦宮物語』・『明月記』・『拾遺愚草』

これさえ覚えれば、『新古今和歌集』関連の大学受験文学史問題の9割は解ける!
今回はここまで。
定着させるために、繰り返し問題を解いてくださいね。
『新古今和歌集』の基礎知識を確認しておきたい場合はこちらのページを確認してください。
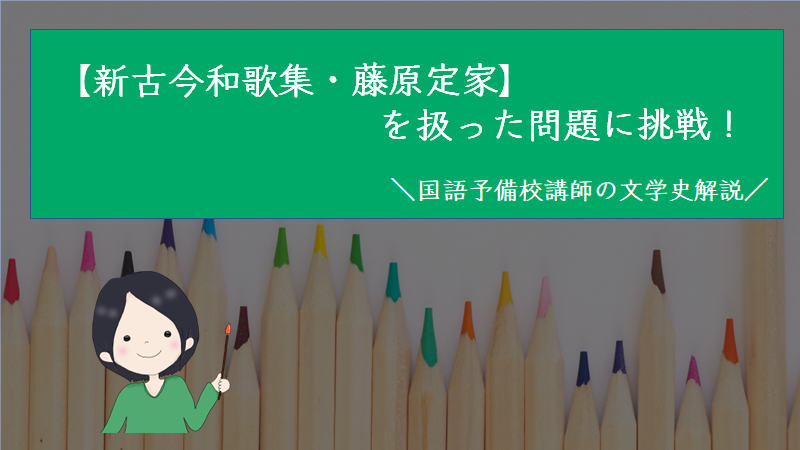
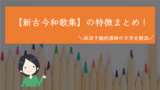


コメント